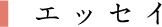仕事の関係で、東京郊外の、ある住宅メーカーの研究所をたずねた。
現代住宅の最新の設備について説明を受けたあと、敷地の裏に建っている、
それぞれの時代を象徴するモデルハウスを見せてもらった。どの住宅も、その時代の最高の技術と設備を備えたすばらしい住宅だった。
価格は、上ものだけで、それぞれ数千万円から億の単位で、ためいきをつきながら見てまわったのだが、
ただ、どの家の、どのフロアーの、どの部屋にも何かが足りないような感じが残った。それはちょうど、
家の壁にぽっかりと空いた穴のようなもので、高度な技術や最新の設備をもってしても、どうしても埋めきれないもののような気がした。
たまたまなのだけれど、その研究所は、私が学生時代に暮らしていた町にあった。
当時、私が下宿していた家とそことは、数百メートルと離れていなかった。なつかしさもあって、私は、研究所を訪ねる前に、その思い出の場所に足を運んでみた。
当時の家はすでに別の家に建て替わっていて、表札の名前も変わっていた。
ただ、猫のひたいのような細長い小さな敷地には、おそらくそうするしかないのだろう、当時と同じような二階建ての白い家が建っていた。
私の部屋は、小道に面した二階の角部屋だった。三畳の部屋には、机と本箱と衣料ケースがあって、寝るときは、机の下に足先を入れて寝た。
そこで何があったわけでもなかった。貧乏と、陽がすっかり昇りきって目をさまし、「さて、今日は何をしようかな」と考えあぐねるような、
ひたすら怠惰な毎日だった。手にしていたものといえば、そうした無限の自由と、漠然とした、ほとんど根拠のない、将来に向けた淡い希望があっただけだ。
でも、もしも神様から、どの時期でもいい、もう一度、おまえさんの好きな時代、場所に還らせてやろうと言われれば、私は迷うことなく、この頃を選ぶだろう。
人間とは、なんと複雑で、なんと不可思議な生き物なのだろうか。
また、なんとわがままな生き物なのだろう。地下室から二階のテラスまでついた、
太陽光発電の耐震構造設計の家よりも、人は、若き日の、小さな三畳の棲(すみか)を選ぶのである。