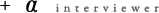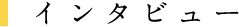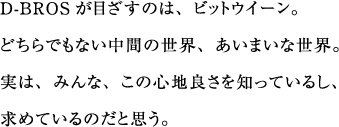
長年、デザインオフィスの(株)ドラフトで、同僚の渡邉良重(わたなべよしえ)さんとともに、D-BROSのブランド名で、数々のヒット商品を手がけてきた植原亮輔(うえはらりょうすけ)さん。「hope forever blossoming」と名づけられた、水を注ぐことで立体的な美しい花瓶に変身する商品を見かけたことのある人も多いはず。一見、子供のあそびのようなアイディアと、それを形にしていくデザインスキルの高さで、競争の激しいデザイン界にあって、まったく独自の世界を作り続けるクリエイター。この1月、渡邉さんとともに、デザインオフィス「キギ」を立ち上げ、新たなチャレンジが始まった。
―まず、渡邉さんと組まれるようになったきっかけから教えていただけますか。
植原―二人の持ち場が違うようなところがありますから、問題ないですね。僕は、どちらかというと、コンセプトやアイディアを考えることが多い。表現も、写真やタイポグラフィーやシンプルなグラフィック表現など。良重さんは、自分の世界観を表現するタイプかな。イラストが主体ですし、何よりも描きたくてしょうがない。それと二人でやるって、一人よりも、ずっとパワーが出るんです。最近の仕事は、プロジェクトを進めて行く上で課題が山積みでしょ。二人なら、そこをなんとか切り抜けられることが多いんです。プロジェクトを成功させることの方が大切なので、ひとりでADとしてやりましたということはあまり気にしていません。ひとりでやるものや複数でやるもの、いろいろあったうえで自分の輪郭がぼんやりみえてくれば良いのではないでしょうか。時代的にもそのような空気があるような気がします。
―フラワーベースも、そういう二人の協力から生まれたのですか。
植原―そうですね。あるとき、僕が、仕事の途中だった詰め替え用のシャンプーのパッケージに水を入れたまま、机の上に置いて帰ったんです。そして翌朝、会社に来てみると、良重さんが、それにお花を差していた。でも、それがそのまま商品になったわけでもなくて、やっぱりシャンプーパッケージの筒状のままだと、良くないんですね。それから、約半年後、実際に花瓶のかたちに熱で圧着してつくってみると、本物の花瓶に見えてきて、それから順調にデザインが進みました。
 左|「HOTEL BUTTERFLY」サイト扉ページ画像 / 右|フラワーベース「hope forever blossoming」
左|「HOTEL BUTTERFLY」サイト扉ページ画像 / 右|フラワーベース「hope forever blossoming」―もうひとつ、人気の「ホテルバタフライ」の仕事も、とてもおもしろいですね。これは、架空のホテルを創り上げて、そのホテル関連グッズを次々と作っていくという、ブランドというものが人の心の中に創り上げられるものだとしたら、まさにその本質を突いた作品という気もしますが、きっかけはどうだったのでしょうか。
植原―実をいうと、これを考えたときは、ポスト「フラワーベース」を営業チームから切望されていたときでした。アイディアって出すのは簡単ではないですよね。そこで、デザイナー以外の人たちからもアイディアが出る仕組みができないものかと考えていた時に出来たのが「ホテルバタフライ」なんです。ホテルというのは広がりがあるでしょ。だから、ホテルと蝶という表現の核さえ作れば、デザインという切り口以外にも、いろんなスタッフからアイディアが出てくるのではないかと考えたんです。例えば、こんな良い素材があるからデザインしてみない?とか、こんな企業と組んでホテルグッズを作ってみたら?など。ホテルという場所はミニチュアの社会なんです。しかもちょっと特別な。様々なモノやコトがあります。ドラマもあります。だからアウトプットもデザイン商品以外に、小説や音楽、さらに映画にまで広がるでしょ。可能性をいっぱい持っているんです。それで実際に音楽はつくりました。作曲家の阿部海太郎くんにお願いしてつくっていただきました。
―なぜ、バタフライ?蝶蝶だったのでしょうか。
植原―蝶って、とても面白い存在だと思うんです。昆虫だから、当然、三次元の生き物なのですが、羽だけ見ると、二次元的な美しさもあるでしょ。蝶は、二次元と三次元の中間の生き物なんですね。そういうところが、僕たちD-BROSの商品コンセプトにぴったりでした。僕たちのデザインはビットウィーン、つまり、ユーティリティ&トイ、リアリティ&ファンタジー、グラフィック&プロダクト、こうしたどちらでもない、中間に位置する、あいまいな世界にあるんです。そして、実はみんな、この心地良さを知っているし、求めているのでは?と思うことが時々あります。例えば、朝、起きる前の、寝ているわけではないし、といって、はっきり目覚めているわけでもない、まどろみの時間、これって心地いいでしょ。恋人同士っていうのも、まったくの他人でも、身内でもないあいまいな関係。そういうグレーなところはどこか不思議な気持ち良さがあります。
―最後に、この1月から、渡辺さんといっしょに「キギ」というデザインオフィスを立ち上げられましたが、新しい環境でのお仕事はいかがですか。
植原―やはり、気合いが入りますね。いままでと違う闘争心が湧いてきます。今、下に正式なデザイナーがいないので、自分でデザインをすることが多くなりました。10年前に戻った感覚で仕事をしてますが、デザインすることがまた楽しくなってきました。しかし経営も含めて、仕事の種類が増えたのは確実です(笑)。ドラフトとはこれからも良い関係で仕事をしていきます。もちろんD-BROSの仕事も。そして、5月にはgggギャラリーでキギの展覧会をやることになりました。本も出版する予定です。これからの僕らの動きにも是非注目してください。