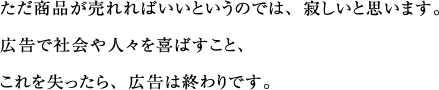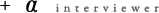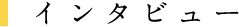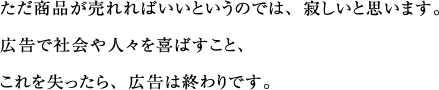
電通時代は、松下電器、資生堂、トヨタ自動車などを担当し、多数の広告賞を受賞。テレビコマーシャルの黄金時代を牽引してきた小田桐昭(おだぎりあきら)さん。加えて、小田桐山脈といわれる多数の優秀なクリエイターを育て、現在、活躍しているクリエイターたちに多大な影響を与え続けている。電通を退社ののち、2003年オグルヴィ・ジャパンCCOに就任、
この3月まで、同社の取締役名誉会長。広告に対する信頼と情熱は、他の追随を許さない。イラストレーション、絵本作家としての活躍も有名。
―まずうかがいますが、近ごろの広告が、おもしろくない原因は何でしょうか。
小田桐―宣伝部の人たちの関心が、社内にばかり向かっているからでしょうね。社内の人たちが、宣伝部がどれくらいがんばっているか確認するには、テレビでたくさんの広告を打った方がわかりやすい。自分の会社のCMが、テレビにたくさん流れれば、「ああ、ウチも宣伝をやってるんだな」という感じがしますから。でも、たくさん流しているだけで、少しも消費者に届いていない。この会社の創設者であるオグルヴィの語った言葉に、「家族に見せたくないような広告を打つな」というセリフがあります。家族とは消費者でしょう。もし、出来上がった広告が、家族にも見せたくないような広告だったとしたら、それは、消費者に向けたものではない、ということになりませんか。それは、たんに上司や重役たちの顔色だけをうかがった広告だということになります。今の企業の宣伝部の人たちは、自分の会社や商品のことを、ほんとうに、大切に思っているのでしょうか。
―他にも、広告がつまらなくなった理由はありますか。
小田桐―テレビコマーシャルのほとんどが、15秒CMになっていることもあるでしょうね。15秒ですと何も言えない。15秒CMばかりになった理由には、コンビニ対策のために、とにかく本数を打たなければいけないということがあると思いますが、おかしいのは、コンビニで売っていない企業の商品まで15秒になっていることです。クルマや家電は、コンビニで売っていないでしょ。たぶん、広告を信じていないのですよ。良い広告を作れば、人の心も動けば、商品も動く、さらに社会も動く。こういった広告の力を信じていないんですね。
―競合で制作代理店を決めることも、もう当たり前になってしまいました。
小田桐―そうですね、どこが広告制作を担当するのか、代理店を競合させるのも、アイディア競争という意味では良い面もありますが、やはり弊害の方が多いと思います。競合は勝たなければ始まりませんから、どうしても勝つことが主眼になってしまう。たとえば、クライアントの決定権者がどんな広告を好むかの競争になってしまい、ほんとうにその企業がどうあるべきか、商品を売るためにはどういうコミュニケーションが最適かなどという肝心なところが、どこかに行ってしまうのです。そういう意味で、競合ばかりだと、良い広告ができなくなってしまうのです。
―しばしば議論になることでもあるのですが、そもそも良い広告とは何でしょうか。
小田桐―オグルヴィの言う、良い広告とは「商品を売る広告」です。感動的な作品でも、見事な広告でもなく、「これは知らなかった。この商品を試してみなくちゃ」と言われるような広告です。オグルヴィは、若いころの5年間、ガスレンジを売るセールスマンをやっていたことがあった。そのころ経験した、商品を売るむつかしさを生涯の糧として持ち続けた人です。ただ、大切なことは、商品に手を出してもらい、それが売れるためにはまず、広告を見てもらわなければいけない。まずは、消費者の心を動かすことです。オグルヴィの作った広告が、たんに売らんかな広告ではなくて、広告史に残るような名作が多いのはそのためです。逆に、今の広告は誰も見ないし、心も動かない広告ばかり。これでは、商品が売れるわけがない。
―どんな広告を作っても、モノやサービスが動かない時代になったとも言われていますが、そのあたりはどうお考えでしょうか。
小田桐―最近、日本人の欲望がなくなった、ということが前提になっていますが、その考え方は、おかしいと思いますね。宝島社が出している「スィーツ」という雑誌は、100万部も出ているのを知っていますか。昔にくらべて、雑誌が読まれなくなっている時代に、100万部は驚異でしょう。この欲望はどこにあったのでしょう。宝島が引き出したということでしかないわけです。もう少しいえば、今の日本をつまらなくしているのは、広告界の人の責任も大きいと思いますね。とくに、電通や博報堂のような大きな広告会社の人たちの責任は大きいと思う。広告がおもしろくない社会って、やはりつまらない社会ですよ。さきほど、オグルヴィの「商品が売れる広告」という話をしましたが、広告がコミュニケーションであるかぎり、やっぱり、もうひとつ広告には大きな仕事があると思う。ただ商品が売れればいい、というのでは寂しいと思います。広告で社会や人々を喜ばすこと、これを失ったら、広告は終わりです。
―ネット広告の比重が、どんどん増してきて、広告手法そのものが変化しつつありますが。
小田桐―新しく出てきたネットメディアにしても、伝えるということについては、これまでのマスメディア主体の時代と、基本的に変わるところはないと思いますね。むしろ、表現の拙さを、メディアの変化にかこつけているのではないでしょうか。
―以前のような、広告が社会やモノを動かしていた時代を取り戻す、名案はありますか。
小田桐―広告界で経験を積んだ人が、企業の宣伝部に行くという手法もあると思います。アメリカの大手企業の宣伝担当者の多くは、広告業界の出身者たちです。代理店との仕事の仕方とか、ほんとうに広告の世界がよくわかった人が、企業の宣伝部を率いればもっと違ってくるはずです。広告会社の営業を長くつとめた人なら、クリエイティブやマーケティングのこともよくわかっているはずですから、こういう人たちが、どんどん企業の側に入っていけば、また広告の世界も活気が出てくると思いますよ。
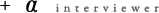
広告界では、かねてから、「広告の神様」とよばれている小田桐さんである。その理由は、ご自身がこれまで作ってこられた作品がすばらしいこともあるが、加えて、広告を見る目が図抜けて優れていることだ。われわれ凡庸なものから見れば、まるで広告の良し悪しを判断する虎の巻を隠し持っているかのようなのだ。そのため、今でも自分の作った広告作品への意見を聞きに、氏のもとを訪れるクリエイターは少なくない。もうひとつ、この世界の人たちが小田桐さんを敬愛してやまないのは、氏が、広告を心底、愛しているからだ。それは徹底していて、むしろ、広告のためには自らを顧みないような感じさえ受けることがある。だから、氏の広告界への提言は、聞く人によってはときに辛辣に届く。だが、そうした直言は、かならず愛情のこもったものでもあるので、こちらの心に柔らかく突き刺さるのだ。