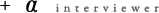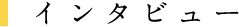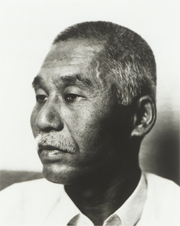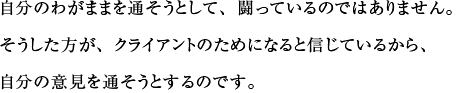
1950年福岡県生まれ。東京育ち。68年東京都立工芸高校デザイン科卒。スタンダード通信社、サン・アド、仲畑広告制作所を経て,現在副田デザイン制作所主宰。作品に、トヨタ「ECOPROJECT」「ReBORN」、
サントリー「ウイスキー飲もう気分」、シャープ「AQUOS」、高橋酒造「しろ」、ANA「ニューヨークへ、行こう」、earth music&ecologyなど。
―最初に、副田さんがお仕事を始められたころの広告界の状況からおうかがいしたいのですが。
副田―私が仕事を始めるころまで、実は、広告表現ではデザインの方が優位に立っていたのです。
ところが、1980年代に入ると、仲畑貴志さんの「好きだから、あげる」や、糸井重里さんの「おししい生活」のあたりから、
むしろ、コピーの方が主役になってきたのです。ある意味、私以前のデザイナーは、コピーはあまり好きでなかったのですね。
―今は逆に、デザイン主体の広告が多くて、コピーは片隅に追いやられている気もしますが、そのあたりはどうお考えでしょうか。
副田―私は、コピーは骨格で、デザインは肉体だと思っています。コピーのない広告というのは、私には考えられません。
音楽でいえば、作詞と作曲がうまくかみ合ってこそ名曲が生まれるわけで、
例えば、ビートルズでいえば、ジョン・レノンの詞とポール・マッカトニーのメロディーがうまく合わさって、すばらしい曲になったのだと思います。
―たしかに副田さんの作られる広告は、コピーがきちんと立ったものが多いですね。
副田―広告は生活者の一番近くにある表現でしょう。広告は企業から消費者へのコミュニケーション活動ですから、
その場合、言葉というのは絶対に欠かせないと思うのです。例えば、サントリーのBOSSの広告で言えば、「このろくでもない、すばらしき世界。」
というしっかりとしたコピーがあるから、トミー・リー・ジョーンズの演じる広告シリーズが、うまく展開していくのだと思います。
私がADを担当しているトヨタのクラウンの、前田知己さんのコピー「権力より、愛だね」も、やはりクラウンの新しいイメージをきちんと言い表している良いコピーだと思います。

―副田さんが広告づくりにあたって、大切していることを教えていただけますか。
副田―強いて言えば、人の琴線に触れるというか、さぐるというか、そうした点でしょうか。
よくある二流のものは、表層的で、「それっぽい」ものばかりです。もっと日本人の情緒って深いものだと思うのです。
雨という表現ひとつをとっても、英語ならRAINで済んでしまいますが、日本語は、小ぬか雨、霧雨、小雨、あるいは、どしゃぶりまで本当に多彩でしょう。
広告主の言いたいことを一方的に押しつけるのではなく、見る人に何か感じてもらう、ここが一番のポイントだと思っています。
例えば、最近のコマーシャルを見ていると、アメニティが全然感じられませんね。そんな思いで、少し前に私が作ったのが、
熊本の米焼酎「しろ」((https://www.youtube.com/watch?v=f7B4k-Lm1Lo)のコマーシャルです。
この焼酎はどんな味だとか、こんなにおいしいとか言う必要はなくて、CMを見ている人に、こんな生活がしたいな、幸福って日常の中にあるんだな、
と思ってもらえれば、それでこちらの言いたいことは消費者にじゅうぶん届くのだと思います。

―ただ、現実の広告づくりの現場では、クライアントさんの意見がどうしても強く反映されてしまいがちだと思うのですが。
副田―おっしゃる通りかもしれません。そして、クライアントの言うとおりにした方が楽に決まっています。
でも、それははっきり言って、クライアントさん自身のためにならないのですよ。こちらは、自分のわがままを通そうとして闘っているのではありません。
そうした方が、クライアントのためになると信じているから、自分の意見を通そうとするのです。その意味でいえば、最近は、広告づくりの現場にパッションが欠けて来ているような気もします。
資質も大事ですが、「いい仕事がしたい」という情熱が必要だと思います。
これは、岡田准一さんが演じるNHKの黒田官兵衛の広報ポスターです。写真は藤井保さんで、ふつうならスタジオ撮影で終わるところだったかもしれません―「わかりました、スタジオで撮りましょう」って。
でも、それならありきたりのものしか出来ません。そうではなくて、実際のロケの現場に行って、スタッフの方に嵐の中の戦場の雰囲気を作ってもらいました。
そのため、岡田さんの顔なんてはっきり写っていません。でも、この方がずっと、官兵衛が生きている。そして、役者としての岡田さんも生きていると思うのです。

人と同じことをやっていたら、絶対にだめです。僕は、「椅子取りゲームの舞台に上がるな」と、よく言っています。みんなと同じステージ上がって椅子取りゲームをしたって、競争が激しいだけです。
ゲームに参加しないで、自分の椅子を持って座る方がいい。自分だけの闘いの場を別に作る。僕はそこでしか、良い仕事は絶対に出来ないと思っています。
―最後に、副田さんのように、広告デザインの世界で活躍することを目指している若い人たちに、何かアドバイスのようなものがありましたら、お聞かせください。
副田―そうですね。人との出会い、ものとの出会いを大切にして欲しいですね。私は、仲畑さんをはじめ、今なら佐々木宏さんなど、本当に広告の天才と呼ばれる人たちと仕事をして来ました。
それが、今の私を作ってきたように思います。多くの人は、これほどの機会に恵まれることはめったにないと思います。ただ、「男は黙ってサッポロビール」のアートディレクター、細谷巌さんと仕事をしたことはありません。
出会ったのは、細谷さんの広告作品だけです。そして、その広告に衝撃を受けた。そのときに思ったことは、「上には上があるなあ」ということでした。そこで、ヨシと思った。
つまり、そうした天才たちに実際に出会うことはなくても、作品からも同じように強い影響を受けて、がんばれることもできるわけです。こうした、人と、ものとの出会いをぜひ大切にして欲しいと思います。