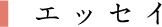今書いている本の原稿を、ある編集者に見せたら、したたか叱られた。何を言いたいのか、まったくわからないという評価だった。その編集者は、私が初めて本を書いたときの編集者だ。
三十年たっても、こちらに少しの進歩がないどころか、むしろ退化しているように見えたのかもしれない。
私がはじめて本を書いたのは、一九八0年代の半ばころ、まさにバブル全盛の時代だった。そのせいで、出版社自体も景気がよく、ある意味では、何を書いても許されたようなところがあった。
そうした甘い時代にデビューしたせいで、ものを書くコツも、社会に自説を発表する所作も、私は誰からも指導を受けることなく、ここまで来てしまったのだ。
叱責の手紙を受け取った二、三日は、それを見る気もしないくらい腹立たしい感じがしていたが、少し落ち着いて読み返してみると、指摘はいちいちもっともで、むしろ指摘どおりに筋を組立て直した方が、読み手にとっては、ずっとわかりやすいことに気づかされた。
大学教員のような仕事をしていて、ときどき思うことは、誰からも叱られることがない、ということだ。会社なら上司がいる。
自営業のようなことをしている人でも、得意先や、商品を買ってくれる消費者から厳しい叱責を受けることもあるだろう。
それに対して、教授のような肩書きをもらうと、世間からはそれなりの扱いを受けるし、まして学生から叱られるようなこともない。まさに、頭の上に天井のない仕事なのである。
湖北の高月に、滋賀県が誇る国宝の仏像、渡岸寺(どうがんじ)観音堂の十一面観音像がある。十一面のお顔は、それぞれやさしい表情だったり、
人々を励ましたり、いろいろなのだが、そのうちひとつの「瞋怒(しんぬ)相」は、邪悪な人々をいましめて正しい道に向かわせる、怒りの表情をしている。
仏像の中にも、不動明王に代表されるように、怒りの表情をしたものも無くはない。ただ、人々の救済が目的であるはずの観音像で、なぜ怒りの表情の面が付いているのか、それを見たとき、不思議に思っていた。
人はしばしば、ほめられたり、なぐさめられたりすることで、救われる。ただ、ある場合には、厳しく叱られることでも救われることがあることを、昔の人もよく知っていたに違いない。