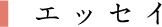脚本家、山田太一さんのエッセイはどれも魅力的だが、そのひとつに「逃げていく街」(新潮文庫)という作品がある。その中にこんな文章がある。
「私は少し自分が嫌いな人が好きである。あるがままの自分で何が悪い? とひらき直ったような人は苦手で、自分の欠点を知っていて、なるべく隠そうと努め、出来たらあるがままよりよりは、少しはましになりたいと考えているような人が、どちらかといえば好きである」。
少しだけ自分が嫌いな人とは、とりもなおさず、自分の欠点や弱さについて認識しているということだろう。それをなんとか修正しよう、また人に見せまいとするところに、謙虚さやつつましさが生まれる。
戦後、日本のジャーナリズム界をリードした評論家の大宅壮一(1900?1970年)が、「下士官型人間」の性格をいくつかあげている。下士官とは、昔の軍隊の位の呼び名で、陸軍でいえば軍曹などがこれにあたるのだが、大宅はそうした人々の特徴をいくつか指摘している。その中のひとつに、彼らは「反省する、疑う、恥じる、はにかむ、てれるといったような面がほとんど見られないこと」 というのがある。さきほどの、山田太一さんがあげた性格の人とは、およそ真反対の人たちだ。
外に対して、自分をどう見せるか、ということでいえば、こんな話もある。
その昔、ブラッシーというアメリカ人プロレスラーがいた。ニックネームは「銀髪の吸血鬼」で、決め技は相手の額に噛みつくというおそろしく原始的なものだった。だが、意外なことに、母親に対してはたいへん優しい人だったらしい。ある日、母親から「リングの上のお前と、私が知っているお前と、どちらが本当のお前なの」と問われたところ、ブラッシーは、「どちらでもない」と答えたと言う。
この話は、私の記憶の片隅に残っていたもので、本当かどうか確証のある話ではない。しかし、ブラッシーを知っている人なら、一度聞けば、忘れられない話であることだけは確かだ。