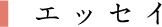坂井眞理子「母の想い出5」2013年
坂井眞理子「母の想い出5」2013年いつも連絡をもらいながら、行きそびれていた知り合いの画家の展覧会に足を運んだ。彼女と私は同郷である。
同じ高校の何年か先輩になるのだけれど、故郷をアートで盛り上げようという運動を一時期していたこともあって、会えばすぐに意気投合する仲だ。
個展の開かれていたギャラリーは、東銀座の歌舞伎座の前の通りをはさんで、少し路地に入ったところだった。
小さなマンション風の建物の二階が会場で、ギャラリーの主人と十分くらい話をしながら待っていたら、本人が現れた。
アーチストというのは、不思議に年をとらない。もちろん外見は、それ相応に老いていくのだが、何十年前と今の時間とが、きちんとつながっている。
昔と今が、同じ人なのだ。人に使われている人生を送っている人は、職場が違ったり、部署が変わったりすると、そのつど、人が変わっていく。
そうして、かつての話題は、いつか思い出話になるのだが、アーチストにはそれがない。個性だけを頼りに生きるということが、自然と、人をそんな風にしてしまうのだろう。
去年の春、池田20世紀美術館で開かれた彼女の回顧展に話が移ったところで、「故郷では、やらないの」と水を向けてみた。
もちろん彼女自身もそれを願っているらしいのだが、あるとき、その美術館の関係者から「うちは、死んだ人の展覧会しかやりませんので」と断られたそうだ。
彼女は現代アートの作家である。作家が生きているうちに作品を紹介しない現代アートというものが、あるのだろうか。
それは、―私たちの美術館は、現代アートに不理解ですので、と言っているのと等しい。
新しいものを理解し、それについて自信をもって評価することはかんたんではない。
ただ、好みの部分を超えて、年を経た人には、つねに新しいものを理解しようと努める義務があると思っている。
多くの場合、権力や財力を持っているのは、古い人たちの側だからだ。実際に時代を切り拓くのは新しい人たちだが、先に生まれた人たちは、それを手助けする大切な義務を負っているはずだ。
彼女はもう年齢的には、新しい人ではないかもしれない。でも、このかた半世紀を超えて、いつも新しい絵を描いている。