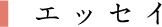昨日、ある人と打ち合わせをしていて、「ブランド」という言葉を使うことが、ふと、自分でもわずらわしくなった。
こんな気持ちは過去にも確かあったような気もするが、それは、新幹線の中で、ちょっと行儀の悪いご婦人が、たまたまブランドもののバックをかかえていて、
そのマークに何だかいやな感じを受けたときのことだったかもしれない。そんなネガティブな体験にまつわることなしに、
その言葉をやりとりすること自体が、少し鼻をつくように感じたことが、意外だった。
企業も、最近では自治体も、「ブランド」づくりにいっしょうけんめいだが、その根拠はといえば、消費者が「ブランド」に固執している、という一点だけだ。
ブランドエクイティの考え方も、山ほどのブランド本が書店に山積みになっているのも、マーケティングを専攻している大学院生たちが、
必ずといってよいほどブランドをテーマに論文を書きたがるのも、ただただ、商品に手を出す人たちがそれにこだわりを持っているからに過ぎない。
だが、ある日、それまで吹いていた風がぱたりと止むように、満ちていた潮がいつの間にか沖の方へ向かい始めるように、
ブランドの狂騒も、やがて終わりをつげることだろう。
そして、気になるのは、その「ブランド」時代がいつ終わるか、ということだ。
その質問にすぐさま用意できる良い答えはないのだが、むしろ、もう終わり始めているのではないだろうか、とも思う。
僕たちの気持はとても気まぐれだから、昨日までそうおっしゃっていましたよね、といくらせがんでも、もう遅い。
ブランドの本質は、企業の中にあるものでも、商品の中にあるものでもなく、人の心や町の中に漂う空気のようなものだから、
そういえば、そんなこともありましたね、くらいで、消えて行くものでしかない。
瀬戸内の海に近い町で育った私は、潮の満ち干を知るのに、二とおりあることを知っている。
ひとつは、浜に寄せる波を注意深く観察することだ。寄せる波には大小があって、一度や二度見たくらいでは、満ち潮なのか引き潮なのかわからない。
それでも何度か見ているうちに、満ちていればそれなりに浜に潮がさしていることがはっきりとわかるようになる。
そしてもうひとつは、海には不思議と雰囲気というものがあって、浜に立っただけで、たとえば、これは引き潮だな、と気配から感じることがある。理由はない。
潮の干満も人のすることも、そう変わりはないはずだ。ブランドの潮目は、僕の中では、すでに引き始めている。