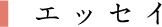誰にも、ふるさとがある。こういう言い方をすると、では東京の人はどうなるのか、と関東では尋ねられたものだが、
やはり、東京生まれの人も、東京がふるさとになるのだろう。
私は山口県の生まれだ。瀬戸内海側の、宇部という、昔、炭鉱で栄えた町に生まれ育った。
堀り出された石炭は、坑口から港まで貨車で運ばれる。だから貨車の走る線路は、わりと町の中を通ることになる。
急なカーブのところでは、山積みになった石炭が、揺れと傾斜のせいで、バラバラとこぼれ落ちる。貨車の通り過ぎた後、
それを待ち構えていた子供や女性たちが、われ先に拾い集めて家に持ち帰り、燃料にしていた。そういう情景を今でも夢で見ることがある。私のふるさとにかぎらず、日本全体が貧しかったのだ。
それに比べれば、かつての何倍も、何十倍も、私たちのくらしは豊かになった。ただ、それは、東京や大阪などの大都市を入れて、
日本全体を平均的にならしたときのことであって、私たち一人ひとりがかかえているふるさとが豊かになったかどうかは疑問だ。
おそらく私だけではないと思うけれど、自分のふるさとは、昔に比べて、すっかりさびれた町になってしまったというのが、
少なからずの今の日本人の実感ではないだろうか。かつては買い物客でにぎわっていた町の繁華街も、今ではバスもたまにしか止まらないような閑散としたところになってしまい、
本屋もレストランも、町はずれのロードサイドに移ってしまったというのが、ほとんどの地方都市の現状に違いない。
近ごろ、よその国が攻めてきたらどうするとか、誰も見たこともないような島が、どこの国のものだとか、
そういった議論には国をあげて夢中だけれど、自分たちの生まれた町がどんどん消えて行くことには、あまり関心がないようだ。
戦闘機を飛ばして、海底の油田を掘ることよりも、もっとまじめに考えるべきことがあるような気がする。
「人はこの世に生まれて初めて吸った空気を肺の一番奥にしまい込んでいる。だから故郷は、誰もの心の奥深くずっとある」―うそのようだけれど、
いや本当かもしれないと思わせる、どこか心にひびく言葉だ。