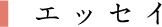いつもより少し遠回りの道を散歩していたら、疏水沿いにある高校の門の前に出た。休みの日だったけれど、おそらく部活の練習なのだろう、
吹奏楽部の練習の音が校舎の裏手あたりから聞こえてきた。きれいにそろった音ではなく、それぞれが、めいめいのパーツを吹いている管楽器の音色だった。
私は楽器の世界にはまったく縁のうすい人だが、その練習音を聞いているうちに、中学だったか、高校だったか、あるいはその両方だったかもしれないが、
陽の落ちかかった時刻に学校の門を出るころいつも、遅くまで練習に励む吹奏楽部の音色が、背中の方から聞こえてきたことを思い出した。
例えば、学生時代のことを思い出す場合、それは人によって、グラウンドに響く野球部のノック音だったりするかもしれない。
だから、何かの機会に、金属バットの乾いた打球音を聞くときには、おそらく母校のグラウンドの隅々までの情景が、その人の目に浮かんでいることだろう。
音の記憶とは不思議なものだ。それは耳だけの記憶ではなく、空間と時間とがきちんと合わさった、目にも鮮やかな記憶なのだ。
劇作家の寺山修司(1935?1983)が、あるとき、自分の演劇の海外公演費用を捻出するために、オーディオメーカーと組んで、
世界の著名人と音楽にまつわる対談をシリーズで行うという、広告紙面づくりをしたことがあった。その中の対談相手のひとりに、スペインの画家、
サルバドール・ダリが登場したときのキャッチコピー「音楽は、忘れようとしても忘れられない思い出をつくる」は、今でも名コピーとして語りつがれている。
私の母は、今年のはじめ、施設で亡くなったが、最後の十年ほどは認知症をわずらっていた。そこの施設で聞いた話だが、かなり症状が進んだ患者でも、
その人が若いころにはやった流行歌などを聴くと、中に、涙を流す人がいるとのことだった。おそらくその人の目には、曲にまつわる青春時代の想い出の情景が、昨日のことのように鮮やかに浮かび上がっているのではないだろうか。