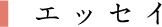大阪の中之島にある美術館を訪ねた帰りに、淀屋橋の駅まで歩いていると、ちょうど市役所の横あたりに、今はやりのマルシェ風の出店が並んでいた。
そんなに数は多くなかったが、野菜や果物、ジャムやはちみつ、中にはあまり聞いたことのない国のコーヒー豆を売る店があったりして、けっこうな人だかりがしていた。
最近、東京などに出かけたときも、えっ、こんなところに、と思うような広場にも、こうしたマルシェを見かけることが多くなった。
マルシェとは市場のことで、英語でいえばマーケットだ。パリにいたころ、私の住んでいたアパルトマンのすぐ裏手でも、火曜日と木曜日に朝市型のマルシェが開かれていた。
ガイドブックによれば、こうしたマルシェは、常設のものも含めてパリ市内だけでも80くらいあるそうで、それぞれの地域で、週の決まった日にカラフルなテントの出店が、広場や大通りに並ぶのだ。
パリのマルシェと日本にそれとの違いは、規模の大きさもさることながら、パリでは、マルシェは日々の生活に欠かせない存在という点だ。
街にも日本のようなスーパーもあることはあるけれど、そこでは生鮮食品は売られていない。また、パリ名物のパン屋さんやカフェは多い一方、魚や野菜を売る店は少なく、
そのため住んでいる場所によっては、マルシェなしでは暮らせないということにもなるのだ。私が今でも、マルシェの立つ日をはっきりと憶えているのは、新鮮な野菜や魚が手に入る曜日が待ち遠しかったせいでもある。
その意味からいえば、マルシェはまさに、パリの人々にとっての生活必需品なのだが、彼らがマルシェを捨てて、常設の大型市場をあまり建設しないのには、
別の理由があるようにも思われる。それについては、うまい表現が見つからないのだけれど、イベント性、そしてそこから生まれる臨時のコミュニティのようなものと言うことができるかもしれない。
いつもは、ただ人が通るだけのマロニエの並木道に、突然、色とりどりのテントが並び、見たこともないようなチーズが山積みになっていたりすると、週のうちの何日かお祭り気分にさそわれる。
また、毎日顔を会わせるわけではない客と店の主人の間では、よっ、久しぶりじゃないか、といったやりとりも、きっと交わされることだろう。
もともとマーケットには、モノとモノとを交換する場としての役割だけではなく、人と人が直接顔を合わせるコミュニケーションの場としての役割もあったはずだ。
フランス生まれのマルシェには、そんな響きが今でも残っていてとても好きだ。