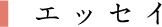自分でいうのも気ひけるが、私はわりと整理の良い方だ。ただ、ときどき、探している本がどこに行ったのか、わからなくなってしまうことがある。それも、埃をかぶったよけいな本はゴロゴロしているのに、肝心の本が見つからない。ちゃんとあの棚の、あのあたりに積んでおいたはずなのに。
別に決めているわけではないが、何年に一回か、本の棚おろしをする。大掃除もかねて、めったに手にしないような本は、思い切って捨ててしまうのだ。まさか、そのとき捨ててしまったのだろうか―そんなはずはない、あの本にかぎって、と途方にくれる。
だが、こんなとき決まって、その見つかり方に法則めいたものがある。自分が想像していた本の装丁とはまったく違ったものだったり、文庫本と思っていたものが新書だったりするのだ。ほんとうに不思議。
だから、手こずった本さがしになってしまった場合には、いったん、自分の想定イメージを真っ白にしてしまう。そうすると、間もなく見つかる。なあんだ、こんな本だったけ、という具合にだ。
こういうのを思い込み、と言うのだろう。そして、本探しにかぎらず、これは私たちの日常と言っていい。次の話は、近著「モノから情報へ」にも書いたものだが、こんな思い込みの例もある。
海外のあるジャーナリストによれば、日本に関する記事の場合、本社が求めるネタは、最初からほぼ決まっているのだと言う―「欧米のマスコミが日本を取り上げるときは、重要なニュースよりエキゾチックな話題や笑える話が選ばれがち。相撲の記事、捕鯨やオタク文化、性的に欲求不満な主婦、女子高生の売春、自殺などは需要が多い。この5年間、私が郵政民営化について書いたのは500語の記事一本だけだが、芸者については長い記事を数本書いた」(「ニューズウィーク日本版」2007年9月19日号)。
スペインに暮らした頃、私も「ゲイシャとダンナ」の関係について問われたことがある。しかも、質問してきたのは、近所に住む、お人形さんのようにかわいらしい小学生の女の子だった。外人の目から見ると、京都に住むおじさんは、みんなダンナに見えるのだろうか。