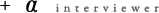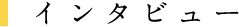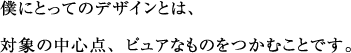
サントリー「伊右衛門」、日産自動車「SHIFT_」、資生堂「一瞬も 一生も 美しく」、それぞれが、時代を画すような広告作品を手がけて来た永井一史(ながいかずふみ)さん。しかもそれらは、一時的に盛り上がりをみせる、いわゆるキャンペーン型広告ではなく、息長く続くブランド創造型の作品が多い。近年は、そうした企業関連広告だけではなく、環境問題などの社会的テーマにとり組む仕事も増えてきている。デザインを通して、企業と社会の新しい価値づくりを押し進めてきた人である。
―永井さんのお仕事を拝見していますと、大きなキャンペーンを打ち上げるというより、伊右衛門や資生堂の例のように、じっくりブランドを作り上げていくという感じが強いのですが。
永井―広告はどちらかというと、生産者サイドからのアプローチで、ブランドは、消費者側からのアプローチのような気がしています。そこが、僕にとっては、非常に新鮮で、魅力的に感じられるのです。ブランドは、広告のようにダイナミックなものでなくて、消費者の日々の暮らしから作られるもので、そうした消費者の思いが社会化されるときに、どうしても表現が必要になってくる。その橋渡しをするのが、僕たちクリエイターの仕事だと思っています。

―永井さんのもうひとつの特徴は、いつどんなときでも、永井流の洗練された美しさが感じられる点だと思うのですが、そのあたりは、つねに意識されているのでしょうか。
永井―何か課題に取り組むとき、対象の本質をつかみたいという思いが常にありますね。別の言葉でいうと、中心点を見つけたい、という気持ちとでも言ってよいでしょうか。そのものに内在している一番いいところ、そこを表現する。だから、僕の表現は、料理でいえば、生のままの素材を生かすということです。余計なものを付け加えたり、こんなことをしたらみんなが喜ぶだろう、なんていうことはしませんね。僕にとってのデザインとは、対象の中心点、ピュアなものをつかむことです。そのあたりが、見る人には、美しさとして感じられるのではないでしょうか。

―近年、エコに関するような、社会的テーマの仕事も増えているようですが、これには何か理由があるのでしょうか。
永井―2005年から2006年くらいにかけてだったと思いますが、「広告批評」という雑誌で、エコクリエイティブの特集があって、それに参加したのですが、そのときに思ったことは、環境保全テーマは、すでにコミュニケーションの時代からアクションの時代に入っているのでは、と感じたことです。そこで提出したのが「クリエイティブ・ボランティアやります」という作品でした。つまり、自分たち自身も、エコのためのボランティアをやります、と宣言した作品で、正直、とんでもない数の依頼がきたらどうしようと心配していました。・・・現実には、数件の依頼でおさまったのですが。
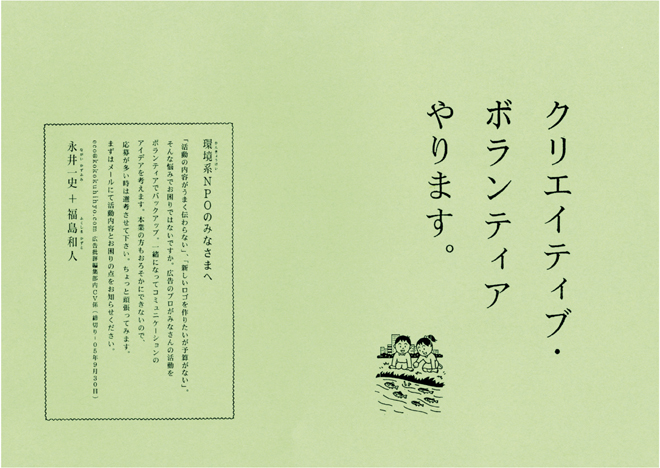
―なぜ、そうした社会的なテーマに、デザイナーの力が必要なのでしょうか
永井―私の考えでは、デザイナーは、時代を感じる独特のセンサーを持っていると思うのです。例えば、デザイナーの作業の特徴は、まず、センサーで何かを感じる、そして、何かに気づき、心を動かされる。そのとき、わりと平気で放っておけなくて、他の人よりさらに深堀りしていく習慣があるのです。次に、それをまとめていく。そして、カタチにして、その結果として、消費者なり、社会を動かす。場合によっては、自分自身が行動に移す場合もあるというわけです。こうした一連の動きが敏感にできるのが、デザイナーと呼ばれる人たちの特徴だと思うのです。
そして、もうひとつは、デザイナーからの需要もあると思うのです。私たちはこれまで、産業の発展に貢献してきました。ところが、デフレの影響で、今、企業からの広告需要の先行きも不透明です。けれど、これまでの広告づくりで培われてきた、独特のセンサーで感じることや、それらを深堀りしてゆき、社会を動かしていくという習性がありますから、社会的な課題を発見すると、じっとしていられないのですね。
―永井さんのように、こうした社会テーマに取り組んだ大きな仕事ができるのは、今の若いクリエイターたちにとって、あこがれの存在のような気がするのですが、こうした仕事ができるようになるまでの、何か良いアドバイスはありますか。
永井―2000年くらいまでは、実は、ブランドコンサルティングなんて、デザイナーにとって、海のものとも山のものとも、つかない仕事だったのです。例えば当時、制作にいる人は、新聞の全面広告を作るような仕事に集中していました。クリエイターにとって、新聞広告でもポスターでも、具体的に何か作らないと、達成感のない時代だった。
そんな中、1999年、「博報堂ブランドコンサルティング」が組織化され、会社になるための準備中だったのですが、そこに私が、マーケッターとか、コンサルの人たちの中へ、唯一、デザイナーとして参加したのです。
―それは何か、お考えがあったのでしょうか。
永井―それまでのような具体的な広告づくりだけではなくて、考え方をデザインするのもおもしろいと思ったのです。結果としてそれが、たいへん良い経験になって、今の僕のバックボーンになっています。つまり、若いみなさんに言いたいことは、社会や会社の基準に合わせていくのではなくて、その時、自分が面白いと思ったこと、正しいと思ったことをやっていく、それが一番大切だと思うのです。