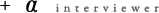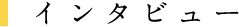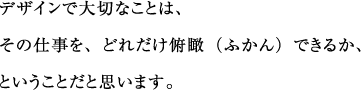
デザイン好きの人なら、「METAPHYS?メタフィス」のブランドは、きっとどこかで聞いたことがあるはず。息を吹きかけると、LEDの明かりがゆらぐキャンドルライト「hono」。ケトルの形をしたユーモアあふれる加湿器「cortina」。そうしたアイディア・機能、そして洗練されたデザインが一体化した「メタフィス」デザインを率いるのが、ムラタ・チアキさん。最近はプロダクトの領域にとどまらず、震災復興、BOPデザイン、エコや地域創生などのソーシャルデザインの領域へも、活躍の場を大きく広げつつある。
―村田さんのデザインオフィスは、ハーズ実験デザイン研究所という、ちょっといかめしい名前ですが、このネーミングの由来から教えていただけますか。
村田―ハーズというのは、英語のhers?つまり、彼女のものという意味です。感性あふれる女性に敬意を表してデザインを行うというのが、僕のデザイン行為の基本にあるからです。そして、実験デザインというのは、イタリアの著名なデザイナーであり、デザイン誌「ドムス」のディレクターもつとめたアレッサンドロ・メンディーニが、かつて「実験デザイン」という活動をやっていたことがあって、それがヒントとなった言葉です。実験デザインというのは、誰かが使った手法は使わないという意味くらいにとっていただければいいと思います。
―もともと大学時代は、応用物理を学ばれたとか。こうしたデザインの世界に入るきっかけは何だったのでしょうか。
村田―大学を出て、三洋電機に入社するとき、デザイン部に入社したくて、デザインを専攻する人たちと肩を並べて、一週間の研修を受けました。その結果、不合格通知をもらったのです。デザイナーには向いていないので、エンジニアなら採用すると。でも、自分としては、あくまでデザイナーの仕事がしたかったので、それをお断りしてデザインの専門学校に入り直すつもりでいました。
ところが、大学の兼松教授の尽力もあって、もう一度、デザイナーとして受験するチャンスを与えられたのです。面接で「今のサンヨーのデザインなら、僕の方がうまくできます」という大失言をしていただけに、二度目の面接にも脈はないと思っていました。デザイン部に入ってからは、製品化に関わる仕事に携われず、結構、苦労しましたね。
この時代の仕事といえば、家電の「its」シリーズのコンセプトがあります。プアーではなくて、ボランタリーシンプリシティ(自発的簡素化)というコンセプトのもと、家電にしては珍しいトラッドブルーという色使いで、コーヒーメーカーやトースター、掃除機など、事業部をまたぐシリーズコンセプトを作り、各事業のデザイナーとの調整を行っていました。その後、オーディオ事業部でやっと、商品化デザインに本格的に携わることができ、結局、四年半、在職したことになります。
―それから三洋をやめられ、独立された後、「メタフィス」というブランドを立ち上げられたわけですが、そのあたりのいきさつについて、お教えいただければと思います。
村田―私がいっしょにお仕事をするのは中小企業が多く、通常のデザイン料をいただくのはむつかしいわけです。そこで、ロイヤリティで、どれだけデザイン費が回収できるかがカギになります。そのためには、制作ロット数をできるだけ多くしなければなりません。そこで考えたのが、ブランド「METAPHYS?メタフィス」でした。コンソーシアムブランドが出来れば、複数の中企業で販路を共有し、ロット数を多くすることが出来ます。それに、メディア知名度の高いブランドは与信機能も生み出します。例えば、「メタフィス」ブランドの商品づくりをするのならばと、メーカーが金融機関から受ける融資もたやすくなるのです。
 吹き消すことのできるLEDキャンドルライト「hono」
吹き消すことのできるLEDキャンドルライト「hono」―そうしたデザイン作業を進める上で、村田さんが、もっとも大切にされていることは何でしょうか?
村田―その仕事全体を、どれだけ俯瞰(ふかん)できるか、ということだと思います。例えば、その企業の経営状態、コアコンピタンス(他社が真似できない核となる能力)、技術力、機械設備、資金力など、あらゆる企業状況を把握した上で進められるのが、デザイン作業だと思います。もし例えば、何かの作業が外注になっていたとすれば、それだけコストがかかってしまいますから。言い変えれば、デザインをするということは、「状況を見切る」ことだと言ってもよいでしょう。
―そうなるとデザインの仕事も少し変わってきますね。
村田―おっしゃるとおりです。ここにコップがあるとして、普通のデザイン作業なら、こんな形のコップを作りましょう、ということになりますが、その企業なりの全体像をきちんと見れば、コップを作ることはやめましょう、という提案になるかもしれません。その意味からも、これからは、あらゆる仕事の中心に、デザインの視点を持った人が立つことが絶対に必要だと考えています。
 左|収納せず、すぐに使えることをコンセプトとしたサイクロンクリーナー「uzu」
左|収納せず、すぐに使えることをコンセプトとしたサイクロンクリーナー「uzu」―村田さんは、最近、ソーシャルデザインの領域でも、活発な活動を展開されていますが、それも、「デザインがすべての中心にある時代」という考え方からでしょうか。
村田―私にとっては、デザインはいつも手段です。何か課題があってはじめて、デザインが必要になると考えています。今年の3月に大阪で「SOCIAL DESIGN CONFERENCE 2012―デザインで日本再生を考える20日間」というイベントを開催しました。エコデザイン、BOPデザイン、地域創生デザイン、震災復興デザインの4つのテーマにしぼって、それぞれの領域で活躍されている専門家やデザイナーの人たちで、トークセッションを行いました。また、それに関連する商品や活動の様子を紹介する展示を、20日間にわたって行いました。
デザインはこれまでのように、商品を使いやすくしたり、少しカッコよくしたりする働きだけではなく、何か問題のあるところすべての領域で力を発揮する、非常に大きな可能性を秘めた手段だと信じています。今、日本が抱えている問題(ISSUE)は、このデザインという手段によって、未来を可視化することができると信じています。
※ BOPとは、Base of the Pyramid 、つまり所得水準を示すピラミッドの底辺部分を指す。こうした底辺部分で暮らす人々は、現在、全世界で40億人と言われ、そうした人々の生活・文化水準の向上や、自尊心の向上などをサポートするデザイン活動が、今求められている。