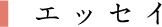http://f.hatena.ne.jp/yukinho
http://f.hatena.ne.jp/yukinhoパリに半年ばかり住んだことがある。二、三年前のことだ。籍を置いていた大学の裏手に、リュクサンブール公園があった。
観光地のひとつにもなっているが、むしろ、パリに住む人たちの市民公園といった感じが強く、テニスコートや遊具施設などもあって、平日の昼間は、子供づれの母親が散歩するようなところだ。
場所がら、何度ともなく足を運んだところだが、日本に帰国する何日か前、滞在中に世話になった教員や事務の人への挨拶のついでに、公園にも寄ってみた。
いつもの並木道があって、奥の開けたところに、大きな丸い池がある。その向こうはパンテオンだ。しばらく歩いていると、なんだか胸がしめつけられるような思いがしてきた。
公園はいつもの公園と変わりないのだけれど、少し様子が違う。これが最後のリュクサンブールだと思うと、木々も、人のいないベンチも、冬枯れの花壇も、ひとつひとつがいとおしく、
去りがたいものに思われた。
私たちは、限られた生を生きている。そんなことは言わずもがなだが、それをはっきりと自覚させてくれる機会が、ときどきだが訪れる。
いつもは平凡に流れる時間だけれど、ちょうど、太いマジックでくっきりと境界を引くような瞬間がやってきて、その境界線が、僕達が生きていることを、鮮やかにあぶり出すのだ。
人づてに聞いた話だが、昔、NHKで、視聴者の寄せた相談に、ゲスト出演者たちが答える番組があった。ある日の相談のひとつに、
「アメリカへ留学した子供が、帰国せずにそのまま学校で勉強を続けたいというのだが、どうすればよいか」という質問があった。
理由は、せっかく出来た現地の友人たちとの別れがつらいからだと言う。
回答者たちは、おおむね、子供の願いを聞いてあげるのもひとつだという答えだった。だが、回答者の一人、映画監督の大林宣彦さんだけは違っていた。
やはり、帰国させるべきだというのだ。「生きていくうちには、何事にも別れがあるということを、子供に教えるべきだ」というのがその理由だった。