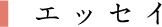小林古径「三宝柑(さんぼうかん)」1939年 山種美術館
小林古径「三宝柑(さんぼうかん)」1939年 山種美術館ある作文コンクールの審査会で同席する作家Kさんの作品を、先日、もう一度読み返してみた。
数年前に映画にもなった、太平洋戦争末期の激戦地、硫黄島の闘いを描いたものだ。戦記というよりも、
硫黄島の守備隊長、栗林忠道(くりばやし ただみち 1891?1945年) の伝記といった方がよいかもしれない。
栗林は、日本でよりもむしろ、General KURIBAYASHIとして、当時の敵国アメリカでの評判の方が高い。
日米戦で、もっともアメリカを苦しめた将軍として知られているのだ。
ただ、本(「散るぞ悲しき」)を読めばわかるのだが、敵国からさえもそれほどに尊敬されている理由は、また別にあるような気もする。人間としての栗林だ。
その名前のとおり、硫黄ガスの噴出する南方の島では、栗林もふくめて日本兵全員が、高熱、
そして極度の水不足に悩まされた。そこに本土からやってきた作戦連絡員が、ありたけの生野菜をみやげに持って来たときのことだ
―「将軍は目に涙、副官に命じ、小刀で雀の餌(えさ)ほどに小きざみにし、連隊長以下できるだけ多くの将兵に分け与えられ、自らは一片も口にされなかった」と、ある。
まったく別の世界の話だが、上京のついでに、茅場町から広尾に移った山種美術館に足を運んでみた。
ちょうど、日本画の巨匠、小林古径(こばやし こけい)と奥村土牛(おくむら とぎゅう)の二人展が開かれていた。
そこで出会ったのが、「調子の高さ」という言葉だった。そう言っているのは土牛の方で、兄弟子でもあった古径の絵のことを、調子の高い絵と評しているのだ。
古径の絵を多少知っている人なら、その絵の「調子の高さ」の意味は、おぼろげにでもわかるかもしれない。
ただ、土牛は、絵そのものだけなく、古径の日ごろからの絵に対する姿勢をふくめて、そう言っているのだった。
ちょうどカバンに栗林の本を入れているときでもあったので、この「調子の高さ」という土牛の言葉がひっかかった。
絵がうまいとか下手とか、戦(いくさ)に勝ったとか負けたとかの話ではない。人がすることの「調子の高さ」とはむしろ、
ことにのぞむ前のことでもあるし、また、それらがすっかり終わった後にも続いている何かのような気がした。