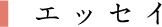義仲寺にある芭蕉の「行く春を近江の人と惜しみける」の句碑
義仲寺にある芭蕉の「行く春を近江の人と惜しみける」の句碑滋賀県のブランドづくりを考える集まりで、県や大津市、あるいは県民全体が、なぜ滋賀と芭蕉のかかわりについて、こんなにも無関心なのか、ということが話題になった。確かにそうだ思う。
発言者の一人によれば、芭蕉が詠んだとされる、およそ900首の俳句のうち、89首が、この近江の地で詠まれたのだそうだ。そうした作品の多さもさることながら、
何よりも、芭蕉自身が、自分が死んだあとに葬るように指定した墓地が、膳所の義仲寺(ぎちゅうじ)なのである。さらにいえば、「行く春を近江の人と惜しみける」の句は、
芭蕉の句の中でも秀逸な作品のひとつだし、俳聖みずからが、「私は近江が大好きだ」と、公言しているようなものだと言ってもよい。
これだけ好条件がそろっていれば、日本国中の俳句ファンや歴史ファンはもちろん、今やおよそ70ヶ国で、それぞれの言語による俳句が作られているというから、
そうした外国人俳句ファンたちが、この滋賀の地に殺到しても、少しも不思議はない。
それをなぜ放っておくのか。もし私が芭蕉なら、「今の近江人は、何ともつれない人ばかりだ」と、あの世で恨みの一句でも詠むかもしれない。
その理由は、少しばかり下品な言葉を使えば、現代において何がお金になるのか、人々がさっぱりわかっていないからだと思う。
今だにほとんどの人たちは、何かを作って売ることがビジネスであり、国や地域の繁栄の源だと固く信じ続けているのだ。けれどそういった仕事が中心の時代は、せいぜい二十世紀までのことだった。
今の時代は、目に見えず、手で触ることもできないものに価値を見出し、それをビジネスにつなげることこそが、中心になっているのだ。芭蕉はもう何百年も前に死んでしまった人だし、
どんなにすばらしい俳句でも、たかだか十七文字の世界ではないか、などとタカをくくっている人には、二十一世紀のビジネスは永遠に手に入らない。
と、ここまで書いて、他人の無知をあげつらっているばかりでは、卑怯千万、天国の芭蕉翁から見れば、私も同類のそしりを逃れられないのではないかと気づいた。
まだ遅くない。妙句はひねり出せなくても、翁をあっと言わせる妙手の糸口くらいなら見つかるかもしれない。少し頭をひねってみることにしよう。