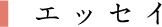故郷の友人から、同窓会の誘いが来た。中学時代の友人だった。夏休みに故郷に帰る予定のないことを告げたら、ちょっとガッカリした声になった。でも、すぐ気をとりなおして、たまには故郷のうまいラーメンでも食べに帰って来いよと言ってくれた。彼は、勉強はあまり出来なかった方だ。また、誰からも満場一致で好かれるタイプでもない。でも、たまに同窓会でもやろうよ、とみんなを誘うのは、いつも彼なのだ。
すぐ後に、高校時代の同窓会の誘いも来た。こちらの幹事も、いつもきまってS君だ。S君もクラスのリーダーという存在ではなかった。そういった集まりの場でも、けっして座持ちの良い方でもないはずだ。ところが不思議に、もうS君しかいないという具合に、卒業以来の幹事が続いている。
私自身が教員としてのゼミ卒業生のクラスで、唯一、毎年、開かれる同窓会がある。私の誕生日あたりに行われ、もう十年ばかり続いている。こちらの幹事はK君だ。K君は在学当時にゼミ長もやっていたが、どちらかというと、みんなからいじられるタイプの学生だった。
そのK君に忘れられない思い出がある。三回生のときのゼミ旅行の時だった。京都駅から淡路島に向かう定期バスに乗るために、朝、八時くらいの集合だったかと思う。一人の女子学生が遅刻して、K君の携帯に電話をかけてきた。今、ホームに降りたところで、集合場所すらわからないと言う。出発まで、一、二分しかなかった。迎えに行っても、ホームに駆け上がるまでで、それくらいかかってしまう。
私はやめろ、と言ったのだが、K君はバスを飛び出して行った。貸切りバスではない。他の乗客もいる。間に合わないだろうが、二人で、後からなんとか追いかけてくるだろうと思った。
出発の時刻をわずかに回ったくらいの時だったと思う。K君と女子学生がバスに飛び乗って来た。みんな一瞬、何が起こったのかと思った。「間に合いました」と、息せき切って報告するK君に、私は唖然とした。
自分のことよりも、仲間のことの方を強く思う人がいる。とても、私にはできないことだ。利害も何もないとき、人はこういう人に付いて行くのだろう。そして、僕たちがいつまでも仲間でいられるのは、こういう接着剤のような人がいるからだ。