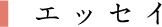BY MICHIKO HISAFUJI
BY MICHIKO HISAFUJIある卒業生の結婚式に呼ばれた。披露宴でのスピーチは、とくにアルコールが入り、宴もたけなわになってしまうと、それをまともに聞く人は少なくなる。その披露宴は、乾杯前のあいさつをのぞけば、いわゆる余興も友人のスピーチもない簡素な進行だった。
キャンドルサービスや、お色直しも終わり、宴も終盤にさしかかったころ、ある年配の女性がスピーチに立たれた。司会から、そのご婦人のことが紹介されると、それまで騒がしかったテーブルから一斉に話し声が途絶えた。
婦人は、息子を交通事故で亡くしていた。そして、その日の新郎新婦の両人は、亡くなられた息子さんの仲の良い友人で、とくに新郎の方は、マンションの同室に暮らしていた間柄だった。深夜のバイク事故である。新郎が真っ先に、救急病院の集中治療室に駆けつけたこと、まだ息のあった数日間、新郎が何度も病院に来てくれたことなどを、声をつまらせることもなく、たんたんと話された。息子さんは、新婦の方とも親しかったようだった。婦人のスピーチの少し前に上映された、新郎新婦の紹介スライドの中に、亡くなった息子さんと新婦のツーショットの写真も混じっていた。
新郎新婦の出会いは、その息子さんの七回忌の場だった。婦人は、二人を結びつけたのは、おそらく天国の息子がそうしたのだろう、そして、今日、こういう場に呼ばれたことは、なんだか、息子のそばに来れたような気がしてとても嬉しいと言われて、スピーチを終えられた。
小説家の伊集院静さんのエッセイの中に、「あの子のカーネーション」という、息子を亡くした母親の心情をつづった小品がある。母親は、伊集院さんの母である。伊集院さんの弟は、故郷の海難事故で亡くなっている。母親は、海から揚がった息子の遺体に取り付いて、検死の医師にこう叫ぶ―「先生、どうか息子を生き返らせてくださいませ」。
息子を失った母の悲痛な気持ちは、常人の想像を絶するものだろう。そこをあえてスピーチに立たれた婦人の心情、そして、そういう場を作った新郎新婦に、言いようのない感動を覚えた。