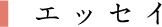依頼ごとがあって、建築家のT・Iさんに、30年ぶりに再会した。再会したといっても、先方は、30年前の私の認識はない。
広告会社につとめていた頃、Iさんの主宰する建築のワークショップに、一か月くらい、通ったことがあった。
テーマはたしか、「ノマド(遊牧民)のパオをつくる」という内容だったと思う。パオとは、モンゴルの遊牧民たちが住む、
移動式の大型テントのような住居のことだ。そのパオのモデルを、参加者たちが一人ずつ作るのである。
Iさんの建築観は、建築とは人間の肌のような存在であるべきで、重くるしい現代の建築を、もっと風通しのよい、
薄い被膜のような存在に開放することだった。そして、今でもその考えは一貫しているように思う。
ワークショップは、都心の建築スタジオの地下の一室で行われた。午後から始まって、夜の方のおしりはなかった。
今から考えれば、優雅な時代で、午後、私は会社をこっそり抜け出してスタジオに顔を出した。
Iさんがスタジオに来られるのは、きまって夕方6時か7時をまわったころだった。時代はまさにバブルの真っ最中で、
Iさんは若手の建築家として売り出し中だったから、昼間はとてもワークショップなどに使える時間はなかったに違いない。
20人くらいいた参加者のほとんどが、建築家そのものか、大学で建築を学ぶ学生だった。
そんな中にあって、建築など学んだこともなく、何しろ好奇心だけで参加していたズブの素人の私など、
とてもIさんの目にとまるような存在ではなかった。ただ、そんな私に対しても、他の参加者たちとわけへだてなく、
熱心に話を聞いてくれた。表情も、話しぶりも実におだやかで、私がスタジオから引き上げるころにもまだ、
居残った参加者の作品を相手に、熱心な議論を続けていたIさんの姿が目に浮かぶ。
会議室にあらわれたIさんは、30年前に、やあ、と言って、地下スタジオに顔をのぞかせたときの表情と、
まったく変わらなかった。メガネの奥の細い目が両めじりに垂れ下がって、にこやかに、おだやかに、実に静かな人、そのままだった。
今回は、30年前の思い出を、Iさんに話さなかった。理由はわからない。
でも、人の間には、触ればこわれてしまうような大切な思い出もあることを、この時、初めて知った。