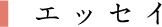ある作文コンクールの表彰式でのことだ。審査員の中で、一番の年長者ということで、私が総評のスピーチのマイクを握ることになった。
受賞者へのコメントは別に機会があるので、選にもれた作品の中から、いくつかの印象に残った文章を読み上げることにした。
そのうちのひとつに、病名はわからないが、長く難病を患い、入退院を繰り返している中学生の作品があった。
苦しい闘病生活の中、母の励ましに応えて必死に生きてゆこうとする本人の思いがよくつづられていた。中でも、次のような一行が、私の胸を打った。
「僕は病気と向き合って生きようと思います。退院するたびに、僕は江戸川を流れる風の香りを感じるのです」。
中学生の文章である。江戸川にそよぐ風と、生きていることの実感を、これほど強く結びつけて感じられる人が、他にどれほどいるだろうか。
私は江戸川に行ったことはないけれど、私も同じように川原に立って、生々しい風に吹かれている気さえした。
そういうことを、少し声をつまらせながら、壇上でしゃべった。
表彰式が終わったあと、別の部屋で、受賞者や参列者を招いての立食式のパーティが開かれた。
パーティも半ばくらいまで進んだころ、私のそばに、詰め襟の制服を着た中学生の姿があった。
かたわらには、母親らしき中年の女性が並んで立っていた。その女性が私に声をかけた。「江戸川の中学生は、この子です」。
一瞬、何のことかわからなかった。まさか、重病の中学生が表彰式の会場に来ているなど考えもしなかったからだ。
ただ、色白の端正な顔つきの、いかにも利発そうなその中学生の顔を見て、その親子が誰なのかすぐに了解した私は、
何かを言おうとしたのだが、熱いものがひといきに目がしらにこみあげてきて、言葉にならなかった。
聞いた病名は、やはり難病と言われるもののひとつで、外からはわからないが、その痛みは、つねに激しいものがあるのだと言う。
何もできないので、私はカバンから名刺を取り出して「がんばれ、U君!」と書いて渡した。そして、U君の手を両手で握った。
自分のしたことが、一人の人間の生に、じかにつながるような感じを持ったことは、これが初めてのような気がする。